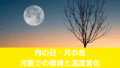月の形が夜ごとに変化していく「月の満ち欠け」は、古来より人々の生活や暦に密接に関わってきました。新月から始まり、三日月、上弦、満月へと変化し、やがてまた新月に戻るこのサイクルには、宇宙のダイナミズムと地球との深いつながりが秘められています。本記事では、新月から満月までの変化を中心に、満ち欠けの仕組みや周期、観察のポイントまでをわかりやすく解説します。
月の満ち欠けとは?

月の満ち欠けとは、地球から見える月の明るい部分(太陽に照らされている部分)が日ごとに変化していく現象のことです。月自体は常に半分が太陽光に照らされていますが、私たちの視点(地球)からはその見える角度が変化するため、形が変わるように見えるのです。
月の主な8つの位相(フェーズ)
| フェーズ | 説明 |
|---|---|
| 新月 | 月が太陽と同じ方向にあり、見えない |
| 三日月 | 新月から約3日後、右に細い弧が見える |
| 上弦の月 | 半分が光る、右側が明るい |
| 十三夜・十四夜 | 満月に近づく、ほぼ丸い形 |
| 満月 | 地球から見える全面が光る |
| 十六夜〜二十夜 | 満月から少しずつ欠けていく |
| 下弦の月 | 左半分が光る |
| 二十六夜・晦日月 | 細く残り、やがて新月へ戻る |
新月から満月までの日数

月の満ち欠けは「朔望月(さくぼうげつ)」と呼ばれる約29.53日周期で起こります。このうち、新月から満月まではおよそ14.77日です。
| 満ち欠け区間 | 所要日数(目安) |
|---|---|
| 新月 → 上弦の月 | 約7.4日 |
| 上弦の月 → 満月 | 約7.4日 |
| 新月 → 満月 | 約14.77日 |
このように、月の形は日々変わっていき、満月は新月から約2週間後に現れます。
満ち欠けの仕組み
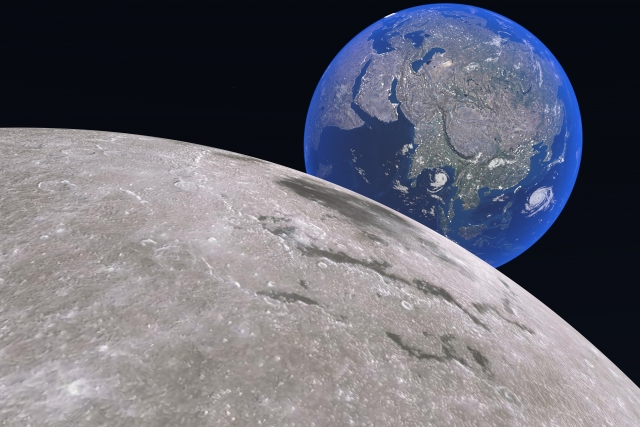
月の満ち欠けは、月・地球・太陽の位置関係によって決まります。
基本構図:
太陽 → 月 → 地球(新月)
太陽 → 地球 → 月(満月)
- 新月のとき:月が太陽と同じ方向にあり、裏側が照らされているため地球からは見えません。
- 満月のとき:地球の反対側に月があり、照らされた面が全面見えるため、丸く輝きます。
月の公転は反時計回りで、地球から見ると右から左へ満ちて、左から右へ欠けていきます。
満ち欠けと生活・文化

月のリズムは人間の生活と密接に関わってきました。
暦と月
- 太陰暦では月の満ち欠けを基に月日が決められており、旧暦の「十五夜」「新月」などの行事もこれに基づきます。
農業と月
- 昔から農作業の計画には月のサイクルが使われ、「満月の日に種をまくと良い」などの伝承も残ります。
神話と信仰
- 月は多くの神話や宗教に登場し、「月の女神」「月の神」など神聖視されることも多くあります。
月の満ち欠けを観察するコツ

月の変化を観察するには、以下のポイントに注意しましょう。
観察のポイント
- 夕方~夜にかけて観察:上弦の月は午後、満月は夕方に東から昇る
- 方角と時刻に注目:満月は日の入りとともに昇り、夜を通して見える
- 双眼鏡や望遠鏡を使うと変化が分かりやすい
[満月] 月の昇る方角と時刻
太陽(西) ← 地球 → 月(東)
夕方:月が東から昇る → 深夜に南 → 明け方に西へ沈む
まとめ

月の満ち欠けは、太陽・地球・月の絶妙な位置関係から生まれる自然のリズムです。新月から満月までは約14.77日というサイクルで、目に見える月の形が日々変化していきます。
このリズムは、古来より農業や宗教、暦など人間の文化と密接に結びついてきました。毎晩少しずつ変わる月を見上げることで、宇宙の動きを身近に感じることができるのです。
次に夜空を見上げるときは、月がどの段階にあるのかを意識してみてはいかがでしょうか。月は、静かに、しかし確実にその形を変えながら、私たちの時間の流れに寄り添い続けています。