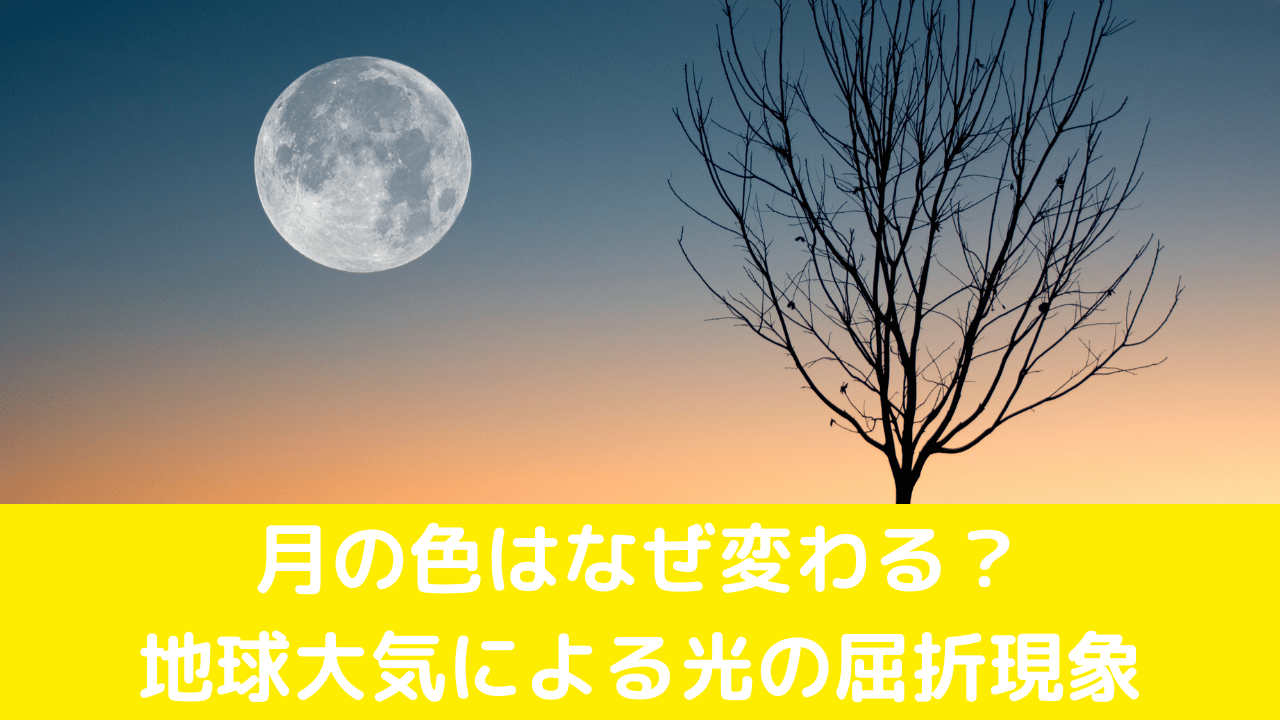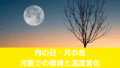私たちが夜空を見上げたときに目にする月は、いつも同じ色をしているとは限りません。白く輝くこともあれば、黄色やオレンジ、さらには赤っぽく見えることもあります。これらの月の色の変化には、単なる視覚の錯覚ではなく、物理的な原因があります。その中でも最も大きな影響を与えているのが、地球の「大気」です。本記事では、月の色がなぜ変化するのか、その仕組みを光の屈折や散乱といった科学的観点から解説します。
月の色が変わるのはなぜ?

月は自ら光を放っているわけではありません。太陽の光を反射して光っているため、観測条件によって見える色が変化します。
主な色の変化と原因
| 月の色 | 見える条件や現象 |
|---|---|
| 白色〜黄色 | 高い位置にある月、空気の影響が少ない時 |
| オレンジ色 | 地平線付近の月、夕暮れや夜明け時 |
| 赤色 | 皆既月食中、地球の影の中にある時 |
| 青白い | 高地や空気が澄んだ場所での観測時 |
これらの色の違いは、「光の散乱」と「屈折」によって説明されます。
地球大気による光の屈折と散乱

太陽光は、さまざまな波長(色)を含んだ白色光です。これが地球の大気を通るとき、波長の違いによって進み方が変化します。
レイリー散乱とは?
波長の短い青い光は、空気中の分子によってより強く散乱されます。これが昼間の空が青く見える理由です。
- 短波長(青系) → よく散乱される
- 長波長(赤系) → ほとんど散乱されない
屈折と月の色
月が地平線近くにあるとき、その光は大気の厚い層を長く通過します。このとき、光が屈折しつつ、短波長の光は散乱されてしまい、地上に届くのは赤系の光が多くなります。その結果、月がオレンジや赤く見えるのです。
イメージ図:地平線近くの月
太陽光 → → 月
↓
~~ → 散乱された青い光
↓
屈折し届く赤い光
皆既月食で赤く見える理由

月食の際、太陽・地球・月が一直線に並び、地球の影に月が入ることで暗くなります。しかし、完全に真っ暗にはならず、月が赤っぽく見えることがあります。
地球の大気が”レンズ”になる
地球の大気は、太陽光を屈折させて地球の影の中にまでわずかに光を通します。この光は、先述のように赤系の光が中心となり、結果的に月は暗赤色に見えるのです。この現象は「ブラッドムーン」とも呼ばれます。
| 月食時の月の色 | 原因 |
|---|---|
| 暗赤色 | 地球の大気を通過した太陽光の赤い成分 |
| 暗褐色〜灰色 | 大気中の塵や火山灰が多い時 |
その他の色の要因

月の色に影響するのは大気だけではありません。以下のような環境要因も見逃せません。
大気汚染や黄砂、火山の噴煙
- PM2.5や黄砂、火山灰などが多いときは、光の散乱がさらに強くなり、月が異常な色に見えることもあります。
観測位置や地形
- 山間部や高地では、大気の層が薄く、青白く輝く月が見えることがあります。
季節と湿度の影響
- 湿度の高い夏場は光がにじみやすく、月が柔らかい色合いに見えることもあります。
月は文化にも影響してきた

月の変化は、古くから人々の生活や信仰、文学にも影響を与えてきました。
赤い月への不安と神秘
- 古代では「赤い月」は災厄の前触れとされたことも。
- 日本や中国では、月食を「天狗の仕業」や「龍が月を食べる」と表現していた地域もあります。
和歌や俳句に詠まれた月
- 「名月や 池をめぐりて 夜もすがら」―― 松尾芭蕉
- 芭蕉のこの句は、静かで澄んだ秋の夜に、池の周囲を歩きながら名月を愛でるという風流な情景を詠んでいます。月そのものを直接形容しているわけではありませんが、月の存在感や季節感を巧みに表現した一句です。
- 古来より、月は日本の和歌や俳句の重要な題材とされ、季節の移ろいや心情を映す象徴的な存在でした。赤く染まった月、雲間からのぞく淡い月、また満ち欠けによる変化など、様々な形で詠まれています。
- 月は感情や自然観を結びつける存在として、多くの歌人や俳人に詠まれてきたことからも、その文化的な重要性がうかがえます。
まとめ

月の色が変わるのは、地球の大気によって太陽光が屈折・散乱される物理的な現象によるものです。特に、月が地平線近くにあるときや皆既月食の際には、赤やオレンジといった印象的な色が現れます。
これらの変化は、単なる見た目の違いにとどまらず、私たちの文化や自然観にも深く関わってきました。次に月を見上げるときは、その色が語る科学と歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。