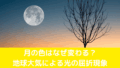夜空を見上げたとき、月の表面に広がる黒っぽい模様を見たことがある人も多いでしょう。それらは「月の海(げつのうみ)」と呼ばれていますが、実際には水が存在する海ではありません。それでは、なぜ「海」と呼ばれているのか?その正体は何なのか?この記事では、月の海の成り立ちや命名の由来、科学的な特徴について、図や表を交えながら詳しく解説します。
「月の海」の正体とは?

「月の海」とは、月の表側に広がる黒っぽい平坦な地形のことを指します。
名前の由来
17世紀、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で月を観察したとき、明るい部分と暗い部分を発見しました。暗い部分は水の海のように見えたため、「海(mare)」という名前をつけたのが始まりです。
実際には何なのか?
実際の「月の海」は、広大な玄武岩でできた溶岩平原です。かつて月内部の火山活動によって噴出したマグマが冷えて固まり、現在のような黒っぽい地形となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実態 | 溶岩で形成された玄武岩の平原 |
| 水の存在 | なし(微量の水分子が岩石中に存在する可能性はある) |
| 色が暗い理由 | 鉄分の多い玄武岩が光を吸収しやすいため |
月の海の形成過程

月の海がどのようにして誕生したのかを、以下のステップで見てみましょう。
1. 巨大隕石の衝突
約40〜30億年前、月の表面には多くの巨大隕石が衝突し、大きなクレーターが形成されました。これが「海」の場所の起点となります。
2. マグマの噴出
月内部のマントルが加熱され、溶岩がクレーターの底に噴出しました。地殻の薄い部分からマグマが上昇したと考えられています。
3. 玄武岩平原の誕生
噴出した溶岩が冷却・固化し、現在の黒っぽい平原となります。これが「月の海」の正体です。
簡略図:月の海の形成
隕石衝突 マグマ噴出 玄武岩の冷却
↓ ↓ ↓
[巨大クレーター] → [溶岩で満たされる] → [平坦な暗い地形]
主な「月の海」の名称と特徴

現在、国際天文学連合(IAU)によって多くの「海」が正式名称として登録されています。代表的なものを表で紹介します。
| 名称 | 日本語訳 | 特徴 |
|---|---|---|
| Mare Imbrium | 雨の海 | 月面最大級の「海」、表側の北西部に位置 |
| Mare Serenitatis | 晴れの海 | 丸く明瞭な形で、観測しやすい位置にある |
| Mare Tranquillitatis | 静かの海 | アポロ11号の着陸地点 |
| Mare Nubium | 雲の海 | クレーターに囲まれた古い地形 |
| Oceanus Procellarum | 嵐の大洋 | 「海」ではなく「大洋」、最も広大な溶岩平原 |
表側に集中する理由
月の海は、ほとんどが表側に集中しています。これは裏側の地殻が厚く、溶岩が表面に到達しにくかったためと考えられています。
月の海と科学的意義

「月の海」は、単なる模様ではなく、月の地質学的な歴史を知るための重要な手がかりです。
地質年代表
- 古期月面(約45億〜40億年前):地殻形成期
- 海の形成期(約40億〜30億年前):溶岩活動が活発
- 静穏期(約30億年〜現在):火山活動はほぼ停止
月の海の岩石サンプルは、アポロ計画などで地球に持ち帰られ、月の年代測定や地質進化の研究に活用されています。
地球との比較
地球ではプレート運動や風化・侵食によって地形が常に変化しますが、月には大気や水がないため、「月の海」は数十億年前の状態をそのまま保っています。
まとめ

「月の海」とは、水が存在する海ではなく、古代の火山活動によって形成された玄武岩の広大な平原です。その名前の由来は歴史的な観測に基づくものであり、科学的には「溶岩原」と呼ぶのが正確です。
月の海は、月の内部活動や形成過程を理解する上で極めて重要な存在であり、今後の探査や研究によって、さらに新たな発見が期待されています。夜空を見上げたとき、その黒い模様の奥にある月の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。